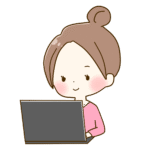倍数算の文章問題|和と差の見分け方をスッキリ解決!
算数の「比」を使った文章問題について、子どもとの家庭学習で学んだことを記録します。
他にもいろいろな解き方があるかと思いますが、私たちはこの解き方で理解しました。
これって和?差?どっちで考えるの?」
先日の家庭学習中、子どもだけでなく私もあれれ?と思わず戸惑ってしまいました。
これって和で考える?、それとも差で考える?
問題によって使い分けるんですよね。
それを説明しようとしたら、私自身がその場でうまく説明できなくなってしまって。
そこで、注目するするポイントを整理してみました。
比の文章問題には他にもパターンがありますが、この記事では「和が変わらない場合」「差が変わらない場合」の2パターンについて書いています。
問題①:水をうつすタイプ(和に注目の倍数算)
はじめ、容器AとBに入っている水の量の比は 3:2。
AからBに18dLの水をうつしたら、比は 3:5になりました。
はじめ、Aには何dLの水が入っていたでしょうか?
ポイント
AからBに水をうつす → AとBの合計の水の量は変わらない
つまり、和に注目する倍数算!
考え方
① はじめの比:3:2 → 3+2で和は5
② あとの比:3:5 → 3+5で和は8
→ 和の数字が違うので、5と8の最小公倍数40で比をそろえる!
はじめ:3:2 → 24:16(合計40)
あとで:3:5 → 15:25(合計40)
→ 和をそろえるために、はじめの比を8倍、あとでの比を5倍にする!
③ AからBにうつした量は、
→ Aは 24 → 15(−9こ分)
→ Bは 16 → 25(+9こ分)
うつした量は 18dLだから、1こ分を求めるには、18 ÷ 9 =2dL
よって、 Aのはじめの量は 24 ×2=48dL
水をうつすときは、合計が変わらない。だから和で考えるんだね!わ(和)かりやすい!
問題②:同じ量を足すタイプ(差に注目の倍数算)
はじめ、容器AとBの水の量の比は 7:4。
AとBにそれぞれ16dLずつ水を足したら、比は 5:4になりました。
はじめ、Aには何dLの水が入っていたでしょうか?
ポイント
AとBに同じ量を足す → 差は変わらない
つまり、差に注目する倍数算!
考え方
① はじめの比:7:4 → 7-4で差は3
② あとの比:5:4 =5-4で差は 1
→ 差の数字が違うので、3と1の最小公倍数3で比をそろえる!
はじめ:7:4 → 7:4(差3)
あとで:5:4 → 15:12(差3)
→ 差をそろえるために、はじめの比を1倍、あとでの比を3倍にする!
③ AからBに足した量は、
→ Aは 7 → 15(+8こ分)
足した量は 16dLだから、1こを求めるには、16 ÷ 8 =2dL
よって、 Aのはじめの量は 7 ×2=14dL
同じ量を足すと、差が変わらない。さ(差)すが差算!
感想
今回のように「えっ、どっちで考えるの!?」と戸惑っても、合計が変わらなければ和、差が変わらなければ差というように考えたらスッキリです。
時間が経つとまた戸惑うかもしれないけれど、再度チャレンジすることですんなり解けるようになれば。
ひぇ〜っとならない算数を目指していきたいです。